目次
犬の腫瘍で最も多い「皮膚腫瘍」ってどんな病気?
犬の皮膚腫瘍は、厳密にはその名の通り、皮膚組織にできた腫瘍(*良性の腫瘍と悪性の腫瘍=癌のどちらも含みます)のことです。
しかし、実際の診察では、皮下組織(皮膚と筋肉の間にある組織)にできた腫瘍も、見た目には、皮膚が盛り上がった腫瘍のように見えるため、飼い主の方には、皮膚の腫瘍として認識されることがほとんどです。
つまり、触ってしこりの確認ができたり、目視で皮膚の様子の異変を確認したり、専門家ではなくても、普段とは違った変化を確認することが可能なのです。
ここでは、皮膚腫瘍は、皮膚組織にできた腫瘍と皮下組織にできた腫瘍を含めて、『皮膚腫瘍』とします。
犬の皮膚腫瘍は、由来組織によって様々な種類があります。
良性腫瘍と悪性腫瘍があることはもちろんですが、見た目には、ただの皮膚の膨らみにしか見えないものもあれば、自壊して炎症を起こすものもあります。
さらには肥満細胞腫のように、刺激を与えることで腫れあがったり、吹き出物のように分泌物が出るような皮膚腫瘍もあります。
進行の速さも、何年もかけて徐々に大きくなるものもあれば、数日でどんどんと大きくなるタイプの皮膚腫瘍もあります。
また、悪性の皮膚腫瘍の中には、その他の臓器に遠隔転移を起こすものもあります。
原因
犬の皮膚腫瘍の多くは、はっきりとした原因はわかっていません。しかし、中には皮膚の扁平上皮癌のように、強い日光を浴び続けることが腫瘍化する一つ要因となるような、原因がはっきりしたものもあります。
また、いわゆるイボのような見た目の乳頭腫は、パピローマウイルスというウイルスが関連していることがありますし、肛門の皮膚に発生する肛門周囲腺腫は、去勢していない雄犬で多く見られ、テストステロンと呼ばれる男性ホルモンが発症要因に大きく関わっていることがわかっています。
症状
犬の皮膚腫瘍は実に様々な病変があります。
皮下組織にできた腫瘍の場合
見た目では異常所見が現れず、ただ膨らんでいるだけのこともあります。しかし、その腫瘍を触ってみると、脂肪腫では弾力がありますが、そのほかの腫瘍は硬くなっていることが多く、皮下腫瘍の中でも違いはあります。
また、腫瘍によっては数日の間にもどんどんと大きくなるものもありますし、数年かけて徐々に大きくなる腫瘍もあります。
皮膚に直接できた腫瘍の場合
膨らみに加えて、皮膚が赤く炎症を起こしていたり、あるいはジュクジュクとした湿疹状になっているものもあります。
さらに自壊を起こしていたり、逆に一見ただの小さなイボにしか見えないようなものもあります。
皮膚腫瘍の中でも黒色腫と呼ばれるものでは、そのほとんどが皮膚に色素沈着を起こしており、周りの皮膚組織よりも黒くなっていることがあります。
このように犬の皮膚腫瘍は、様々な皮膚症状が見られますが、残念ながら、どんな皮膚症状が、どんな皮膚腫瘍に当てはまるのかを、見た目で判断することはできません。
さらには、皮膚腫瘍以外の病気(皮膚炎や皮膚の過形成など)との区別もつきにくいため、皮膚の病変は、見た目で判断することなく、きちんとした検査を受けて、診断をつけることをお勧めします。
また、悪性腫瘍の場合は、ほかの臓器に転移することもあるため、皮膚症状以外の症状が見られることもあります。
犬の皮膚腫瘍の余命
やはり腫瘍の種類によって様々です。
一般的に皮膚の病変だけで死に至ることは稀ですので、皮膚以外の悪性腫瘍に比べて、余命は長くなることが多いです。
しかし、肺や肝臓など、生きていく上で重要な臓器に転移した場合には、余命はより厳しくなります。
また、皮膚腫瘍でも、外科手術による切除が難しい場合には、皮膚の腫瘍自体が炎症など、犬にとって辛い症状を引き起こすことがあります。
その場合は、直接命に関わることはあまりありませんが、非常に辛い思いをさせてしまうため、安楽死を選択せざるを得ない状況になることもあります。
皮膚腫瘍の種類
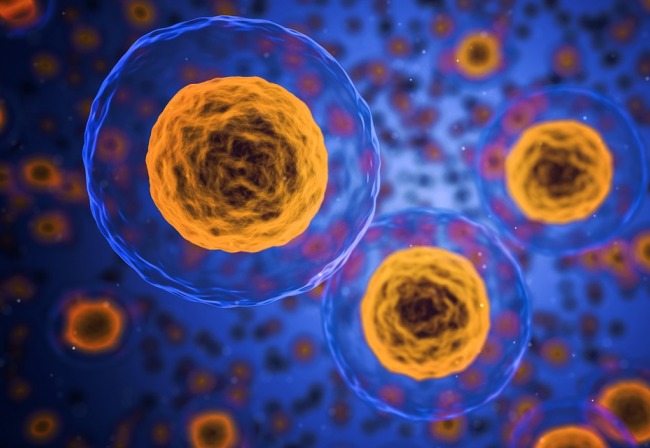
悪性の腫瘍
・肥満細胞腫
肥満細胞腫は皮膚表面のどこにでもできる腫瘍です。ごく小さな腫瘤を形成することが多く、見た目やさわり心地からは判断できないくらい、その形状は多岐にわたります。
悪性度の高い肥満細胞腫は、多発する傾向にありますので注意が必要です。「できもの」があり、それを触っているうちに周囲が赤くなってくる場合には注意が必要です。
・扁平上皮癌
扁平上皮癌は激しく増殖し、見た目は潰瘍のように見えることが多い悪性腫瘍です。日光にさらされる部分に発生する可能性が高く、色素の少ない犬に発生しやすい傾向があります。
毛色の黒い犬は爪の周囲にできやすい傾向があるので、爪の付近にできる腫瘍で悪化や成長のスピードが速いものは要注意です。
・腺癌
しこりの表面が平らでなめらか、また大きくて表面が崩れている場合が多いのが腺癌です。皮脂腺の細胞が腫瘍化したもので、悪性の場合には大きくなるのが早いのが特徴です。
・悪性黒色腫(メラノーマ)
メラノーマは目立たない黒い斑点から急激に大きくなる腫瘤までさまざまです。色は黒いものばかりではなく、灰色や茶色、無色のものもあります。
初期は平坦で黒い腫瘍ですが、進行するにつれだんだん盛り上がってきます。
悪性のメラノーマは大きく、皮膚が潰瘍を起こし細菌感染を起こしていることがしばしばあります。
皮膚にできるメラノーマの多くは良性ですが、爪の根元にできるメラノーマは悪性度が高いので要注意です。
リンパ管や血液から転移し、腫瘍の近くのリンパ節へまず転移し、肺に転移することが多いと言われています。
・皮膚型リンパ腫
皮膚型リンパ腫はシニア犬に発生しやすく、 9~10 歳での発生率が高いと言われています。
なかなか治らない皮膚炎のような経過を取り、膿ほうができたり痒みが強くでたりすることも多くあります。
皮膚型リンパ腫は、できている部分の表面が脱毛していることが特徴です。なかなか皮膚炎が治らないと思っていたら、実は皮膚型リンパ腫だったということもあります。
・肛門腺癌
去勢していない雄犬に多く見られ、良性の肛門周囲腺種と見分けがつきにくい外見をしています。
肛門周囲の腫瘤の進行が早く、潰瘍のようになってしまう場合は悪性である可能性が高くなります。
良性の場合は去勢すると退縮する場合もありますが、悪性の肛門腺癌の場合は退縮せずその後も進行します。
排便がしにくくなったり、手術できずに放射線治療になる場合もあります。
・血管肉腫
血管肉腫はあらゆる部位にできますが、皮膚の血管肉腫は被毛が薄く、皮膚の色素の薄い犬に多く発生します。
また、シニア犬に発生しやすく、特に去勢していない犬に多くみられます。
日光性皮膚炎が認められる皮膚に血管肉腫が起こることが多く、日光が誘発すると考えられています。
良性の腫瘍
・脂肪腫
脂肪細胞の良性腫瘍で中齢から高齢の犬に多く、雌の発生率は雄の 2 倍です。胸部、腹部、四肢、腋下によく発生します。
通常は柔らかく、成長が遅いという特徴があります。
浸潤しながら成長するのではなく、周囲を押し広げ膨張するように成長していきます。
四肢、胸部、腹部に多く見られますが、そのほかの箇所にでも発生する可能性があります。
・組織球腫
組織球腫は高齢犬より若齢犬に多く発生する腫瘍です。ほとんどの場合 2 歳以下で発生しますが、それ以上の年齢でまったく発生しないわけではありません。
組織球腫は急速に成長する円形、ドーム状の腫瘍です。頭部(特に耳)、四肢、胸部によく見られます。腫瘍の表面は毛がなく、光沢があり、潰瘍を起こしている場合もあります。
赤くはれているケースもありますが、犬は痛みや違和感を感じていないようです。
・基底細胞腫
基底細胞は皮膚を構成する細胞の一種でそれが腫瘍化したものです。
中齢から高齢でよく見られ、小型で硬く、皮膚を盛り上げるようにできる腫瘍です。頭部と頚部に発生しやすいと言われています。
・肛門周囲腺腫
去勢していない雄で中齢~高齢の犬で多く発生します。肛門の周囲に盛り上がるような形で発生します。
小さい場合は去勢手術を行うと退縮することもありますが、一般的には腫瘍摘出と去勢手術は同時に行います。
肛門腺癌と初期の外見はほぼ変わりませんので早めに受診することをおすすめします。
犬の皮膚腫瘍になりやすい犬種は?

皮膚腫瘍にかかりやすい犬種は、それぞれの皮膚腫瘍の種類によって変わります。
・扁平上皮癌
犬の皮膚腫瘍で比較的よく見られる扁平上皮癌では、スコティッシュテリア、ペキニーズ、ボクサー、プードル、ダックスフントが知られています。
・黒色腫(メラノーマ)
黒色腫(メラノーマ)は、ボストンテリア、ボクサー、チワワ、ドーベルマン、ゴールデンレトリバー、アイリッシュセッター、ミニチュアシュナウザーなど、多くの犬種が報告されています。
・基底細胞腫
基底細胞腫と呼ばれる犬の皮膚腫瘍では、老齢のブルテリアやビションフリーゼ、シェルティ、シベリアンハスキー、コッカースパニエル
・汗腺の腫瘍
汗腺(皮膚に存在する汗の分泌腺)の腫瘍では、ゴールデンレトリバー、ジャーマンシェパード、コリー、オールドイングリッシュシープドッグ、コッカースパニエルなどが知られています。
・毛包上皮腫
毛包上皮腫では、バセットハウンド、ゴールデンレトリバー、ミニチュアシュナウザー、アイリッシュセッター、ジャーマンシャパードなどが好発すると考えられています。
ただし、犬の皮膚腫瘍を全てまとめると、様々な犬種で発生しますし、もちろん好発犬種以外でも見られることはあります。
そのため実際の診療では、どんな犬種でも皮膚腫瘍を疑う場合には、好発犬種にとらわれず、きちんとした診断を行う必要があると考えています。
例えば脂肪腫は、肥満のメス犬で多い、あるいはラブラドールレトリバー、ミニチュアシュナウザー、ダックスフントなどで多いという報告があります。
しかし実際の診療では、脂肪腫を病理組織診断(外科的な切除が必要な検査)せずに様子を見ることも多く、論文では報告されないケースも多いと思いため、実際には、どんな犬種でもそこそこ多く見られる皮膚腫瘍だろうと考えられます。
治療法

外科手術
犬の皮膚腫瘍の多くは、外科治療、つまり手術による切除が第一選択の治療になります。
良性の皮膚腫瘍の場合:完全に切除することで完治させることができます。
悪性の皮膚腫瘍の場合:切除しても転移などの問題が残ってしまいます。
しかし、転移を恐れて切除せずに腫瘍を残しておくと、炎症を起こして痛みが出たり、化膿したりして、生活の質がとても下がってしまう場合もあります。そのため、手術で切除することも獣医師と相談して検討するようにしましょう。
もっとも手術が第一の選択肢だといっても、手術法の選択が非常に難しくなる皮膚腫瘍もあります。
例えば、肥満細胞腫と言われる腫瘍は、炎症物質を大量に分泌し、手術時は腫瘍だけでなく、その周辺組織を含めて、大きく切除する必要があります。
そのため、例えば顔面など、周辺組織の確保が難しい場所や、肛門や陰茎など、周辺組織を切除すると生命機能が著しく悪化してしまうような場所に腫瘍ができてしまうと、たとえ手術をしたとしても、腫瘍細胞を取り残してしまう、あるいは機能低下を招くなどの手術の代償が非常に大きくなる場合もあります。
また、同じ種類の腫瘍でも、対応が分かれるケースもあります。その一つとして、脂肪腫があります。
脂肪腫は良性の腫瘍で、炎症を起こしたりすることも滅多にないので、手術をせずにそのまま経過観察することも多くあります。
しかし、そんな脂肪腫の中でも浸潤性脂肪腫(筋間脂肪腫)は注意が必要で、脂肪腫が筋肉の間に入り込むタイプの脂肪腫のため、それが動きの妨げになったり、あるいは痛みをもたらすこともあります。
ところが、筋肉の間に入り込んだ脂肪腫は、手術で完全に取り除くことができないため、完治させることが難しく治療に非常に苦慮します。
また、手術が困難な皮膚腫瘍、あるいは手術で腫瘍細胞を完全切除が難しい腫瘍に対しては、放射線療法や抗癌剤療法を行うこともあります。
放射線
放射線治療は、放射線照射装置を持っている施設でしか行うことができない治療法です。
放射線療法がもっとも多く使われるのは、外科手術には不向きな場所にできた腫瘍(脳腫瘍、鼻腔内腫瘍、心臓の腫瘍など)や、大きすぎて手術ができなかったり、手術だけでは取り残しがでてしまうタイプの腫瘍を治療するときです。
一般に腫瘍細胞の方が正常細胞よりも放射線に弱いという特徴があるため、このような腫瘍に対し、腫瘍とその周りの正常組織を含めた範囲にX線を照射します。
すると、照射範囲に含まれる腫瘍細胞と正常細胞の両方に対して、ダメージを与えることになります。
放射線療法の効果は、細胞分裂のときにでますから、常に分裂している細胞ほどダメージが出やすい、ということになります。
つまり、腫瘍細胞のように常に分裂・増殖を繰り返している細胞には大きなダメージを与えられるけれど、分裂していない周りの正常細胞にはダメージが出にくい、というわけです。
ただ、場合によっては障害が起こることもあります。
障害の代表的な例としては脱毛、皮膚の黒変などが挙げられます。
しかし、放射線治療は全身に施せるわけではありません。
体の一部分に限った腫瘍に対して用いられます。そして、照射したところには効くけれども、照射野の外にある腫瘍細胞には一切効き目はありません。
こうした意味で、放射線治療は外科手術とおなじ「局所療法」に分類されます。
これに対して、抗癌剤などの全身にいきわたるお薬で治療するものを「全身療法」と呼びます。
放射線は狙った部位のみにきちんと照射しないといけませんから、ペットが動いてはいけません。そこで治療ごとに全身麻酔をかけて行うことになります。治療回数は治療目的や部位により異なります。
外科手術と同時に実施する場合(術中照射)や数回~9分割(週3×3週)、15分割(週5回×3週)、30分割(1日2回で週5回×3週)などの頻回照射まで、状況に合わせて治療計画がたてられます。
週に1~2回の治療を行う場合、副作用のリスクが高くなります。体の部位によって、正常組織が耐えられる放射線の線量はことなります。副作用を出さずに治療効果を得るために、獣医師と相談しながら照射回数と頻度について飼い主様のスケジュールを考慮しながら計画を進めていきましょう。
外科手術との違い
治療した局所にしか効かない、という点では外科手術と一緒ですが、放射線療法の場合は「照射範囲の中で、正常組織を温存しながら癌組織に効かせることができる」、といったメリットを持っています。
ですから、鼻の中や脳内など、手術で大きく切除することが不可能な場所にできた腫瘍でも、周りの正常組織ごと、広い範囲で照射して、腫瘍組織を選択的に縮めることが可能となります。
ただし、腫瘍の種類によっては放射線の効きやすいタイプと効きにくいタイプがあり、効きにくいタイプの腫瘍では、放射線治療をしても腫瘍が縮まない、短期間で再発する、といったことが起こり得ます。
また、放射線治療は手術の代わりとなるものではありません。このため、無理なく手術で取りきれる場所では、外科手術切除することが多いでしょう。
抗癌剤
抗癌剤治療は、外科手術では取り切れない場合や、診断時に付近のリンパ節や肺などに転移してしまっている腫瘍、悪性度が高く手術だけではほかに転移することがすでに分かっている腫瘍の場合に行います。
外科手術は局所に対する治療になりますが、抗癌剤治療は全身に対する治療となります。
白血球減少や消化器症状など、抗癌剤による副作用も起こる可能性がありますので、定期的に検査を行いながら投与する必要があります。
予防法

犬の皮膚腫瘍を確実に予防できる方法は今のところ、見つかっていません。
しかし、扁平上皮癌の要因となる日光角化症は、日頃から直射日光を避けることで、リスクを下げることができます。
一般的に腫瘍は、慢性的な炎症によって発症リスクが高くなること、そして皮膚は、バリア機能に加えて排泄器官としての役割も持っていることを踏まえると、少しでも皮膚の負担になるような生活を改善することで、皮膚腫瘍のリスクを下げることができるかもしれません。
皮膚は食事中の栄養の約30%を利用すると言われていますので、良質な食事を摂ることが、皮膚腫瘍の予防につながる可能性があるでしょう。
そして、食事に加え、良質なサプリメントも、ドッグフードを利用している犬にとっては非常に大切です。 特に免疫力を高めてくれるサプリメントは、皮膚のコンディションを整えてくれることも期待できますので、ぜひ日常生活に取り入れていただければと思います。
皮膚など犬の身体の組織の成分の半分以上を占めている物質が何だか知っていますか?
実は「有機性の炭素」が過半を占めます。
有機性の炭素は、犬を含むすべての動物は体内で生成できないため飲食から摂取するしかありません。
有機性の炭素を手軽に摂取できる素材が東京大学医学部で研究されており注目されています。
この素材は100%植物由来で化学物質は含んでいません。
体の細胞レベルから元気にして、免疫細胞も活性化されて病気にかかりにくくなることが期待されています。
また抗癌効果も研究の結果確認され、欧米の医療ジャーナルに論文を発表しています。
この、有機性の炭素は今後もさらなる研究がなされていく、希少な素材です。
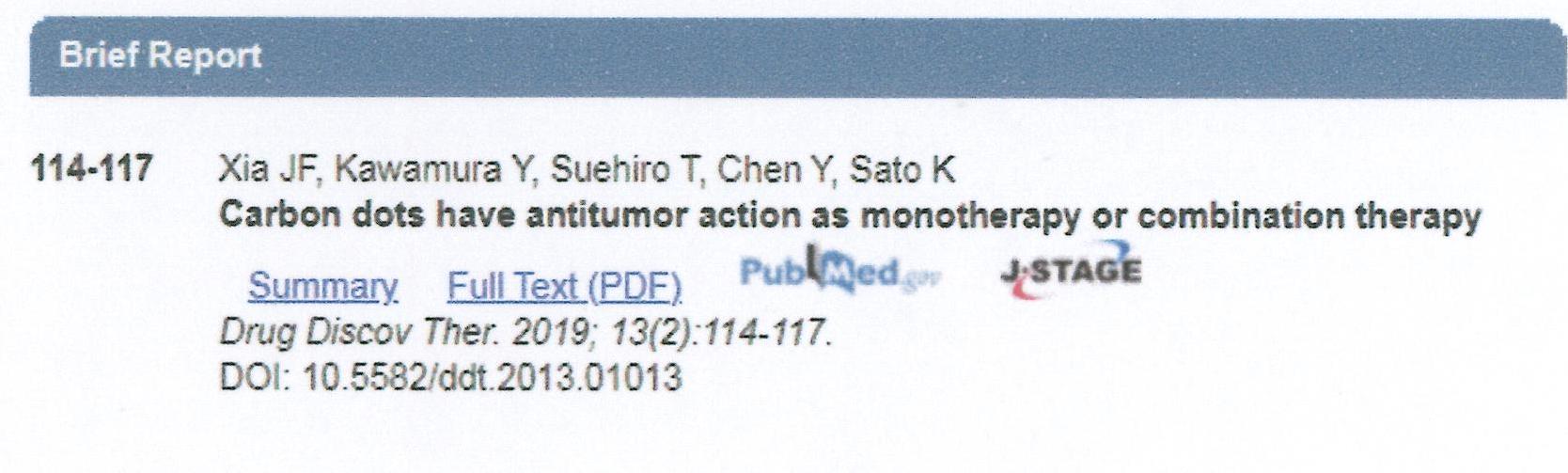
愛犬のために、このような有機炭素を身体に必要な要素を常日頃摂取し免疫力を高めて病気になりずらい体質にしてあげてほしいと思います。
そのためには、仔犬の頃から食事や生活習慣も気をつけてあげてくださいね。



















この記事へのコメントはありません。